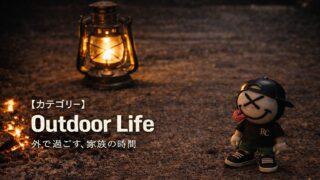親の介護が始まると、子育てや仕事との両立が一気に難しくなります。
「平日は実家の様子を見に行けない」「夜の見守りで寝不足」「夫婦どちらかが仕事をセーブせざるを得ない」──そんな悩みを抱える人は少なくありません。
実際、私も母の骨粗鬆症による背骨の骨折をきっかけに、親の介護と子どもの世話が重なって本当に大変な時期がありました。
病院やデイサービスの調整、買い物、食事の用意…。気づけば毎日が「誰かの世話」で終わっていたんです。
ですが、行政や民間の介護支援サービスをうまく組み合わせることで、心と時間の余裕を少しずつ取り戻すことができました。
この記事では、そんな経験を踏まえて「介護負担を軽くするサービスの実例と活用法」を紹介します。
親の介護で「子ども世代」が抱える4つの悩み
見守り・日中の支援ができず不安になる理由
共働きや子育て中だと、日中に親の様子を見られず「転倒していないか」「食事はできたか」など不安が尽きません。 この不安の根本原因は、「目が届かない時間が長いこと」にあります。 解決するには、見守りカメラやセンサーなどの機器を導入するのが効果的です。
- 設置型センサーライトで夜間の転倒を防ぐ
- スマホで見守れるカメラを導入する
- コープ宅配などで買い物負担を減らす
こうした工夫を取り入れるだけで、毎日の不安がぐっと減ります。
実際に私も介護向けセンサーライトを導入して、母が夜中に安心して歩けるようになりました。
仕事・子育てと介護の“ダブル負担”が起こる仕組み
多くの人が苦しむのが「ダブルケア」です。 仕事・家事・育児に加えて介護が重なると、時間も体力も限界を迎えます。 原因は「一人で全部抱えようとする」ことにあります。
負担を減らすには、次の3つが効果的です。
- 役割分担を明確にする(夫婦・兄弟・親戚)
- 介護サービスを早めに導入する
- 仕事先に事情を共有して理解を得る
私の家庭でも、在宅介護だけでなくデイサービスを組み合わせることで負担が大きく減りました。 ショートステイの体験談も参考になると思います。
介護費用や時間が予想以上にかかる現実
介護は時間だけでなくお金の負担も大きくなります。 交通費、医療費、介護用品など、毎月の支出がじわじわ増えることも珍しくありません。
- 介護用品のレンタルを使う(購入より安い)
- 高額療養費制度を利用する
- デイサービスやショートステイをうまく組み合わせる
私は要介護認定の流れを知ってから、費用の一部が補助される仕組みを理解できました。 制度を知ることが、家計と心を守る第一歩です。
ひとりで抱え込んでしまい“追い詰められる”危険性
介護は「頑張るほど孤立する」側面があります。 家族に頼れず一人で抱え込むと、心身が疲れきってしまう危険があります。
そんな時は、地域包括支援センターやケアマネに相談しましょう。 話すだけでも心が軽くなり、思いがけない支援策を教えてもらえることがあります。
- 地域包括支援センターに相談する
- ケアマネに負担軽減の方法を聞く
- カウンセラーや医師のサポートを受ける
介護は「一人で頑張らない」が一番のコツです。
負担を軽くするカギ「サービス活用」のメリット
公的サービスを知れば“使える範囲”がぐっと広がる
介護サービスは「要介護認定を受けてから」と思われがちですが、実は認定前でも使える制度があります。 たとえば、地域支援事業や見守り訪問などは誰でも利用可能です。
- 市町村の高齢者見守りサービス
- シルバー人材センターの家事サポート
- 介護保険外のヘルパー利用
こうしたサービスを知るだけで、介護の選択肢は大きく広がります。
民間サービスをプラスすれば“時間と心の余裕”が出る
公的サービスだけでは手が回らない部分を、民間サービスで補うのも効果的です。 特に宅食・家事代行・訪問理美容などは、忙しい子ども世代の味方になります。
- 宅配食サービスで食事準備の手間を減らす
- 家事代行で掃除・洗濯の負担を軽減する
- 理美容サービスで外出負担を減らす
私もワタミの宅食レビューで紹介した冷凍おかずを活用しています。 温めるだけで食事ができるので、親も安心して過ごせるようになりました。
兄弟・家族・地域で“分担”することで続けやすくなる
介護は一人で頑張るより、分担することで長く続けやすくなります。 兄弟・配偶者・地域ボランティアなど、少しずつ手を借りるだけで心の余裕が生まれます。
- 週末は兄弟で交代して見守る
- 地域のサロンや高齢者カフェを活用する
- 自治体の「助け合い制度」に登録する
介護は「チーム」で支える時代です。
サービス活用の基本ステップ3つ
親の状態・ニーズを可視化する=何が困っているか整理
まず最初にやるべきことは、親がどんなことに困っているかを整理することです。 思いついた内容を紙に書き出すだけでも十分です。
- 食事・入浴・排せつなど日常の動作
- 転倒や物忘れなど安全面
- 夜間の見守りや薬の管理
これをもとに、必要な支援サービスを選ぶと無駄がなくなります。
ケアマネや地域包括支援センターへ“相談”/申請準備
困りごとを整理したら、地域包括支援センターに連絡してみましょう。 電話で現状を伝えるだけで、どんな支援があるか教えてくれます。
- 要介護認定の申請方法を教えてもらう
- 介護保険外サービスを案内してもらう
- ケアマネを紹介してもらう
最初の一歩を踏み出すだけで、状況は大きく変わります。
公的・民間サービスを“組み合わせ”たプラン作成
最後は、いくつかのサービスを組み合わせることです。 たとえば、デイサービス+宅食+見守りカメラの組み合わせが非常に効果的です。
- デイサービス:日中のケアと入浴支援
- 宅食サービス:栄養バランスを確保
- 見守りカメラ:転倒時の早期発見
組み合わせ次第で、家族全体の生活リズムが安定します。
実例で見る「サービス活用7選」
在宅訪問介護サービスを定期利用する事例
訪問介護は、介護スタッフが自宅へ来て日常の手助けをしてくれる仕組みです。 掃除・食事作り・着替えなど、生活の基本を支えてくれます。
- 週2〜3回の利用から始めると続けやすい
- ケアマネと相談し、必要な時間を調整する
- 慣れた顔のスタッフが来ることで親も安心
初めての介護でも利用しやすく、信頼できる支えになります。
デイサービス・通所サービスを週1〜2回組み込む事例
デイサービスは、入浴や運動、食事の提供などをしてくれる施設です。 家族が仕事をしている間も、親が楽しく過ごせる居場所になります。
- リハビリや趣味活動で気分転換になる
- 入浴サポートで衛生的な生活を維持
- 他の利用者との会話で孤独感を防ぐ
母も週2回のデイサービスを利用してから、笑顔が増えました。
ショートステイで“休日休息”を確保した事例
ショートステイは、数日間だけ施設で親を預かってもらえる仕組みです。 介護を担う家族が「休む日」をつくることができます。
- 旅行や冠婚葬祭の際に活用できる
- 定期利用で親も環境に慣れる
- 家族がリフレッシュする時間を確保できる
私も利用を始めてから、精神的な余裕が生まれました。
福祉用具レンタル&住宅改修で日常動作をラクにした事例
介護ベッドや手すりなどをレンタルするだけで、介助の手間を大きく減らせます。 購入より安く、必要な時期だけ使えるのも魅力です。
- 福祉用具レンタルで介助負担を軽減
- 住宅改修で段差をなくす
- 介護保険で一部補助される
母の部屋も手すりを設置してから、転倒がなくなりました。
配食・宅配食サービス+安否確認で安心を作った事例
宅配食サービスは、栄養バランスのとれた食事を自宅に届けてくれる便利な仕組みです。 安否確認を兼ねて訪問してくれる業者もあります。
- 食事準備の負担を軽くする
- 安否確認で見守りができる
- 食べやすい食材で高齢者にも優しい
私もワタミの宅食を利用して、親の食事準備がとても楽になりました。
民間の家事・介護支援サービスで“家の中”負担を減らした事例
掃除や洗濯、買い物代行など、家の中のサポートをお願いできます。 特に仕事が忙しい時期や、体調を崩した時に頼れる存在です。
- 短時間でも依頼できるサービスが多い
- 親が慣れると生活の質が上がる
- 費用は利用時間に応じて柔軟に設定可能
家事を外注することで、心のゆとりを取り戻せます。
兄弟・家族・地域で役割分担し、サービス+人で支えた事例
サービスだけに頼らず、家族で協力し合うことも大切です。 親との関わり方を家族会議で話し合うと、長く続けやすくなります。
- 曜日ごとに担当を決める
- 地域の助け合い制度を利用する
- 家族チャットで情報共有する
「誰かが必ず見ている」状態をつくることが、最も安心につながります。
7選を使いこなすための“注意点&コツ”
サービスの対象・条件を事前に確認する(利用開始前)
サービスごとに利用条件や対象者が異なります。 申し込み前に確認しておくと、後のトラブルを防げます。
- 年齢・要介護度で利用できる範囲が変わる
- 自治体によって制度内容が異なる
- 利用開始までに時間がかかることもある
不明点はケアマネや役所に遠慮なく聞くのがおすすめです。
親の意向を尊重しながら“使いやすく”設計する
どんなに便利なサービスでも、本人が嫌がると続きません。 親の気持ちを尊重しながら導入するのがポイントです。
- 事前に話し合って納得してもらう
- 無理に増やさず少しずつ慣らす
- 感想を聞きながら調整していく
「一緒に選ぶ」姿勢が、信頼関係を守るコツです。
利用実績・費用を定期的に見直して“ムダ”を防ぐ
サービスを使い続けていると、気づかないうちに費用がかさんでいることがあります。 定期的に見直して、必要なものだけ残すことが大切です。
- 利用頻度と効果を家族で確認する
- ケアマネと一緒にプランを見直す
- 無駄な重複サービスを削除する
見直すだけで、毎月数千円〜数万円の節約になることもあります。
家族間で“情報共有”と“役割分担”を明文化しておく
「誰が何をやるか」が曖昧だと、負担が偏ってしまいます。 メモやチャットで共有すると、トラブルを防げます。
- 曜日ごとの担当表を作る
- 連絡ノートを用意して記録を残す
- ケアマネとのやり取りを共有する
チームで支える意識を持つことが、介護継続のカギです。
今すぐ始める“今日からできる”3つの行動
地域包括支援センターにまず“電話相談”を入れる
どこに相談していいかわからない時は、まず地域包括支援センターへ電話しましょう。 専門職が無料で相談に乗ってくれます。
- 対応は平日の日中が多い
- 親の住所地にあるセンターが担当
- 状況を話すだけでも一歩前進になる
最初の電話が、介護負担軽減の第一歩になります。
ケアマネへ状況を共有し“仮プラン”を立ててもらう
ケアマネージャーは介護のプロです。 現状を伝えると、利用できるサービスを組み合わせたプランを提案してくれます。
- 週何回・どの時間にサポートが必要か伝える
- 金額や補助制度も一緒に確認する
- 変更があればすぐ相談する
頼ることが、最良のスタートです。
今週中に“サービス利用チェックリスト”を1つ作る
できるだけ早く行動に移すために、簡単なチェックリストを作ってみましょう。
- 親の困りごとを書き出す
- 対応できるサービスを調べる
- 優先順位をつけて連絡する
紙に書くことで頭が整理され、次にすべきことが明確になります。
まとめ:子ども世代が“安心して支える”ために
介護の負担はゼロにはできませんが、サービスを使えば確実に減らせます。 重要なのは「自分一人で抱え込まない」ことです。
- 制度を知って使う
- 民間サービスをうまく組み合わせる
- 家族と協力して支える
誰かの助けを借りることは、弱さではありません。 それは家族を守る力です。今日から少しずつ、できることから始めてみてください。