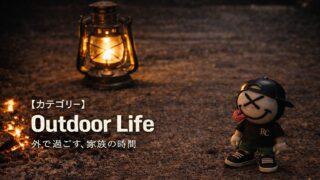「子どもが小さいけど、家族でロックフェスに行ってみたい」と思ったことはありませんか?
近年は、子どもと一緒にフェスを楽しむファミリー層が増えています。とはいえ、実際に行くとなると「暑さ」「トイレ」「荷物」など心配ごとも多いものです。
この記事では、3年前から家族で(個人では15年以上前から)フェスに通っている筆者(ChiRi)の実体験をもとに、子連れでも安心してフェスを楽しむための準備とコツを紹介します。
読めば、初めての方でもフェスを安全に、そして思い出深く過ごすためのイメージがきっとつかめます。
🎸 子連れロックフェス シリーズ
- 子連れロックフェス参戦ガイド2025|家族で楽しむ準備と注意点【実体験ベース】(Vol.1)
- ファミリー向けフェス持ち物リスト2025|暑さ・雨・快適対策まとめ【実体験+便利アイテム】(Vol.2)
- フェス服装 子連れ完全版2025|親子で快適に過ごすための服選びポイント(Vol.3)
- フェス飯・屋台・子連れランチガイド2025|並ばない・こぼさない・飽きないコツ(Vol.4)
- 音楽フェスの撮影禁止ルールまとめ|カメラ持ち込みやSNS投稿のマナー2025(Vol.5)
🎸 はじめての子連れロックフェス
1.1. 子連れロックフェスの楽しみ方
子連れでロックフェスに行く魅力は、音楽を通じて「家族の時間を共有できること」です。音に合わせて体を揺らしたり、芝生でピクニックしたり、楽しみ方は自由です。
最初は「うるさいかな」「子どもが飽きるかも」と不安に感じるかもしれません。しかし、フェス会場にはファミリー向けのスペースやキッズゾーンが用意されていることも多く、安心して過ごせる環境が整っています。
無理にステージ前まで行かず、家族のペースで楽しむのがポイントです。
1.2. まず知っておきたい注意点
フェスは日差しが強く、人の多い環境です。小さなお子さんと行く場合は、次の点を意識して準備しましょう。
- 帽子や日焼け止めで暑さ対策をする
- 休憩できる日陰やテントゾーンを確認しておく
- トイレや水分補給のタイミングを事前に決めておく
特に小さなお子さんは、疲れやすく集中力が続きません。親が時間配分を意識して動くことで、全員が心地よく過ごせます。
1.3. 家族で決める我が家のルール
フェスを楽しむうえで、家族ごとのルールを決めておくと安心です。
- 「必ずトイレは一緒に行く」
- 「迷子になったらここに戻る」
- 「暑くなったら日陰で休む」
こうしたルールをあらかじめ話しておくことで、子どもも安心して行動できます。フェスは予期せぬトラブルも起きるため、事前共有が家族全員の安全を守るカギになります。
1.4. 子ども最優先の考え方を共有
ロックフェスは親にとってもワクワクの時間ですが、子どもにとっては慣れない環境です。音が大きく、長時間の移動もあるため、途中でぐずったり眠くなることもあります。
そんな時は、「無理して全部のステージを観るより、子どもが笑って過ごせる時間を優先する」くらいの気持ちが大切です。フェスの思い出は、“完璧に楽しむこと”より、“笑顔で帰ること”で作られます。
🎒 フェス子連れの準備チェック
2.1. フェス 子連れ 準備の全体像
フェスに行く前に大事なのは、当日の動きを具体的にイメージすることです。
たとえば、会場のマップを確認しておくことで、移動やトイレの不安を大きく減らせます。また、暑さや雨のリスクにも備えやすくなります。
- チケット・リストバンドの確認
- 荷物の仕分け(子ども用・共用)
- フェス飯・水分補給ポイントのチェック
この3つを押さえておけば、当日のトラブルがぐっと減ります。
2.2. チケットと入場の流れを確認
子ども連れでの入場は時間がかかります。チケット受け取りやリストバンド交換の列は混雑しやすいため、早めの行動がポイントです。
フェスによっては、小学生以下の入場が無料だったり、子ども専用ゲートが設けられている場合もあります。事前に公式サイトで確認しておくと安心です。
また、子どもの年齢によっては耳への負担もあるため、キッズ用イヤーマフを用意しておくのもおすすめです。
2.3. スケジュールは余裕ある組み方
フェスは1日がとても長く感じます。子どもが疲れたらすぐに休めるよう、時間には余裕を持って行動しましょう。
- 1〜2組は「絶対観たいバンド」を決めておく
- それ以外は「雰囲気を楽しむ」くらいの気持ちでOK
- 子どもが飽きたら会場探索に切り替える
“詰め込みすぎない予定”が、家族で笑顔のまま過ごすコツです。
2.4. 必ず観たいアーティストは1〜2組
ロックファンとして「全部観たい!」という気持ちはわかりますが、子どもと一緒の場合は欲張りすぎない方がうまくいきます。
我が家では、事前に嫁さんと相談して「お互い1組ずつだけ絶対に観たいバンド」を決めています。残りの時間は子どもたちのペースに合わせて動くようにしています。
このルールを決めてから、フェス全体がぐっと楽になりました。
夫婦で交代しながら、それぞれの「推し時間」を作るのがおすすめです。
🧳 持ち物リストとパッキング術
3.1. 子連れフェスの基本持ち物
子ども連れでフェスに行くときにまず必要なのは、「お子さんが安心して過ごせるアイテム」+「親が動きやすい装備」やよね。具体的には:
- 日焼け止め・帽子・冷感タオルなどの暑さ対策
- レインポンチョ・防水シューズなど雨・汚れ対策
- 首から掛けられる小さなバッグ・おやつ・水筒
これらをあらかじめバッグにまとめておくことで、当日の移動もスムーズになるし、子どもの「疲れた」「寒い」「飽きた」という声にすぐ対応できるようになります。
3.2. 暑さ・雨に強いグッズまとめ
フェス当日は天候が変わりやすいから、「暑さ・雨・風」に備えたグッズが重要です。僕ら家族で使ってるのは:
- 薄手の長袖+Tシャツ重ね着スタイル
- 折りたたみ式パラソルや帽子+日除けシート
- 防水バッグ・携帯防水ケース・靴カバー
この3つを準備しておくことで、晴れてても日差しが強い時間帯、午後の雨、夕方の冷え込み、どれにも安心して対応できるように。
3.3. こども用イヤーマフと耳守り
ロックフェスでは音が大きめやから、特に子どもにはイヤーマフ(耳を守るグッズ)がおすすめ。僕らも長女が6歳・長男が3歳のときから使ってて、効果抜群でした。
- 音にびっくりして泣き出すリスクが減る
- ゆったり後方で観覧してても、子どもが安心して過ごせる
- 親が少し前に行っても「安心して戻りやすい環境」ができる
「子どもが飽きるかな?」と心配するより、まずこの耳守りを投入しておくだけで、全体の安心度がグっと上がります。
🚙 キャリーワゴンと拠点づくり
4.1. キャリーワゴンは使える?確認
フェスによってはキャリーワゴンが使えない会場もあるから、行く前に規約やFAQをチェックすることが大事。もしOKなら、キャリーワゴンは家庭的な“移動基地”として最高やった。
- 荷物をまとめて運べる=疲れ軽減
- 子どもを乗せて移動できる=安心・自由度UP
- 荷物+子ども+休憩スペースと多機能
僕らも「子どもがぐずったら乗せて移動」という使い方で、疲労大幅減につながった経験あり。
4.2. 使えない時は拠点を作ろう
キャリーワゴンが不可の場合でも大丈夫。ステージが見えるもしくは音が聞こえる後方にシートや小さな椅子で“拠点”を作るのが効果的です。
- 荷物を置いておけるから安心感あり
- 子どもが休めるスペースができる
- 親が前に行っても「戻る場所」が決まってるから心配軽減
この“拠点づくり”を早めにしておくと、フェス開始直後の混雑にも強くなって、家族全員がゆったり楽しめる動線が作れるで。
4.3. レジャーシートと小さな椅子
拠点を整えるなら、以下のアイテムがおすすめです:
- 120×180cm程度のブルーシート(シワになりにくい素材)
- 折りたたみ式の小さな椅子2脚(子ども+親用)
- ミニテーブルまたは荷物置きになるトレイ
これだけあれば、“子どもが芝生で遊びつつ親は休憩”というシーンが簡単に作れます。特に子どもが3歳・6歳という年齢の時期には体力の波があるので、椅子がある安心感はかなり大きかったです。
4.4. 親が交代で見張ると安心
フェスで「これ観たい!」と思うステージがあっても、子連れだと全員で行くのは難しいこともあります。うちではこうしています:
- 嫁さんが荷物+子ども拠点キープ
- 自分(ロック好き)が前列に行って思いっきり観る
- 終わったら交代して、嫁さんも好きなバンドの時前に行けるようにする
- 子供が好きなバンドは後ろで楽しむor安全な範囲でいけるだけ前に行って楽しむ
この役割分担のおかげで、親も“自分の時間”を楽しみながら、子どもも安心して過ごせるんです。結果、家族全員が満足なフェス体験に繋がりました。
🚗 会場へのアクセスと動線計画
5.1. 車・電車・バスの選び方
フェス当日は移動で体力を消耗しやすいため、「どう行くか」よりも「どう帰るか」を先に考えるのがコツです。帰り道は混雑必至なので、子ども連れなら以下の方法を検討してみてください。
- 車の場合:早めに駐車場を確保(会場近くのコインパーキングは満車になりやすい)
- 電車の場合:帰りの時間を1本前倒しして予定する
- シャトルバスの場合:始発か終盤を避けて利用する
僕らは基本車移動派で、駐車場から拠点までの距離を事前に調べておくことで、移動中の子どものぐずりを大幅に減らせました。
5.2. 会場マップで動き方を決める
フェスの会場はとても広いため、あらかじめ「どこに何があるか」を把握しておくことが重要です。会場マップは公式サイトやアプリで事前にダウンロードしておきましょう。
- トイレや水道、救護所の位置を確認しておく
- キッズスペースや休憩エリアがあるかチェック
- ステージ間の距離を確認して移動時間を想定
子連れの場合、動線を決めておくだけで一日の疲れ方がまったく違います。安心して回れるルートを作っておくと、当日のトラブルも減ります。
5.3. 人混みを避けるルートのコツ
混雑のピークを避けることは、子どもの安全にもつながります。特にステージ転換の時間帯は人が一気に動くので要注意です。
- 移動は演奏が始まる10分前に済ませる
- 子どもの手は常に握っておくかリストバンドでつなぐ
- 人混みを抜けるときは「すみません」と声をかけて通る
焦って移動すると転倒や迷子のリスクも増えるため、ゆっくりと安全第一で行動しましょう。
フェスって人が密集します。必ずお子様から目を離さないでください。
5.4. 子連れの入退場は早めが吉
開場直後と終演直後は特に混雑します。子連れファミリーは“早めの入退場”が鉄則です。
- 入場は開場時間の15〜30分後が空きやすい
- 退場はラスト1組前に切り上げると渋滞回避できる
- 最後まで見たい場合は、出口近くのエリアで観覧
僕らも「ちょっと早く出る」を意識するようにしてから、帰りのストレスが激減しました。
🎧 観る場所選びと安全な距離
6.1. 後方の安全スペースを優先
ステージ前方は盛り上がる一方で、子どもには危険が多い場所でもあります。おすすめは後方エリアや芝生ゾーンです。
- 視界が開けていて、子どもも落ち着ける
- 音が適度でイヤーマフなしでも快適なこともある
- レジャーシートを広げて家族でリラックスできる
「ステージが遠くても雰囲気で楽しむ」という意識を持つと、家族全員がストレスなく過ごせます。
6.2. スピーカーから距離を取る
ロックフェスのスピーカー音は想像以上に強烈です。音の直撃を避けるために、スピーカーの正面を避け、少し斜め後方に座るのが安全です。
- 音の反響が少なく、耳への負担が減る
- 会話がしやすく、子どもの声も聞こえる
- 小さな子どもが寝てしまっても安心できる
僕の経験では、ステージ端から5〜10メートルほど下がった位置がちょうどよかったです。
6.3. こどもを肩車する時の注意
肩車は子どもが一番喜ぶ瞬間でもありますが、バランスを崩すと危険です。次の点を意識しましょう。
- 人が少ない後方で行う
- 周囲の視界を遮らない高さを意識する
- 長時間の肩車は避けて休憩を挟む
肩車中に手を振るときも周りの観客に当たらないよう注意しながら、安全第一で楽しんでください。
6.4. 混雑時は無理をしない判断
フェスはテンションが上がりやすく、つい無理して前に行きたくなる瞬間もあります。しかし、子どもを連れているときは「あえて引く勇気」も大事です。
- 混雑時は立ち止まって様子をみる
- 危険を感じたら即座に後退する
- 「次の曲まで後ろで観よう」と柔軟に切り替える
家族で安全に帰れることこそ、最高のフェス成功体験です。
🚻 トイレ・休憩・睡眠まわり
9.1. トイレの場所は先にチェック
フェスではトイレ待ち時間が長くなることが多いです。子ども連れの場合は「早め・こまめ」が基本です。
- 入場直後に場所を確認しておく
- 行列ができる前に誘う(特に昼食後)
- 子どもにはトイレサインを教えておく
特に夏フェスでは熱中症対策と同じくらい大切なポイントです。
🛣 帰り道・アフターケア
15.1. 渋滞・混雑を避ける帰り方
フェス帰りは皆同じ時間に動くため、混雑が集中します。一歩早い行動がストレス軽減のコツです。
- 最後の1組前に帰路へ向かう
- 駐車場出口近くに停めておく
- 帰りの高速や電車の混雑時間を調べておく
僕らはこれを徹底するようになってから、帰宅までスムーズで子どももぐずらなくなりました。
15.2. 汗拭き・着替え・軽食の準備
帰りは汗と疲れでぐったりしやすい時間帯です。少しの準備で快適に帰れます。
- タオルと着替えをクーラーバッグに入れておく
- おにぎりやパンなど軽食を車に用意する
- 汗を拭いてから着替えると風邪を防げる
「帰るまでがフェス」という意識で、アフターケアも忘れずに行いましょう。
15.3. 家に帰ったら早めにケア
帰宅後はシャワー・保湿・水分補給をセットで行うのがおすすめです。特に子どもは肌が敏感なので、汗を流してから寝かせましょう。
15.4. 次回へつながるふり返り
フェスが終わったあと、家族で「楽しかったこと・大変だったこと」を話してみてください。
- 良かった点:子どもが喜んだステージやご飯
- 改善点:暑さ・移動・持ち物など
このふり返りをメモしておくと、次回のフェスがもっと快適になります。
🌈 まとめ:家族でロックを楽しもう
16.1. 完璧よりも安全と笑顔を優先
フェスでは「全部のバンドを観たい!」という気持ちもわかりますが、子どもと一緒のときは安全と笑顔を最優先にするのが何より大切です。
- 休みたいときは無理せず休む
- トイレ・水分・帽子の3点を常に意識
- 「また来年も来ようね」と言える終わり方を目指す
フェスの思い出は、観たバンド数ではなく「家族で笑って過ごした時間」の中に残ります。
16.2. みんな違ってOKな楽しみ方
ロックフェスは、それぞれが自分のペースで楽しめる場所です。 ママはフェス飯、子どもは芝生、パパはステージ。みんなの楽しみがバラバラでも、その時間が重なっていることこそが家族フェスの魅力です。
僕自身、嫁さんが後方で荷物を見てくれて、前で1組だけ全力で楽しませてもらえる。そんな時間があるからこそ、家族全員が満たされた気持ちで帰れるんやと思っています。
16.3. 次はライブハウスにも挑戦
フェスに慣れてきたら、次は「子どもと行くライブハウス」にもチャレンジしてみましょう。 フェスより距離が近く、音の迫力もリアルです。ただし年齢制限がある会場も多いため、下調べは忘れずに。
別記事で、子どもと行けるライブハウスや注意点をまとめています👇
16.4. 思い出を写真や日記で残そう
フェスから帰ったら、ぜひ家族で撮った写真やエピソードをまとめてみてください。 「子どもがどんな曲で笑っていたか」「何を食べて喜んでいたか」を書いておくと、次のフェス準備にも役立ちます。
写真は音楽の思い出を閉じ込める宝物。将来、子どもが成長したときに「小さいころフェスに行ったよね」と笑いながら見返す時間は、何より尊い時間です。
こんなカメラを子供に持たせて自由に撮らせてみるのもあとから見ると面白いかもしれませんね。
※ただしアーティストステージの撮影は禁止がほとんどなので使わせる場所は気を付けましょう。
フェスの記録を残すためのグッズを整えると、次回の準備もスムーズになります。
🎵 最後に
子どもと一緒にロックを感じる時間は、ほんの一瞬かもしれません。でもその瞬間が、家族にとって一生ものの思い出になります。
無理をせず、ゆっくり。家族みんなで音を楽しむ。それが“ファミリーフェス”のいちばんの醍醐味やと思います。
また次の夏、会場で笑いながら手を振り合える日を楽しみにしています。
🎸 子連れロックフェス シリーズ